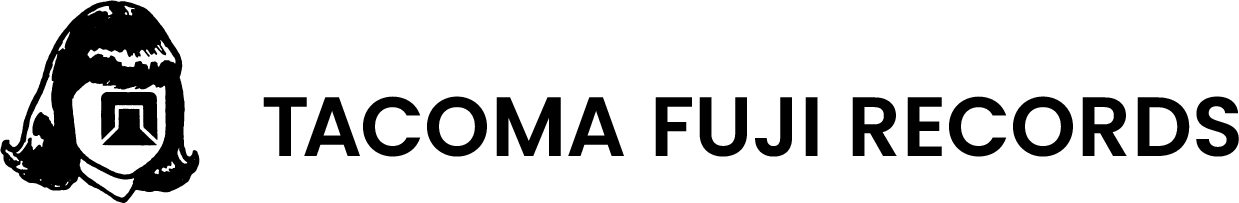hands / 拍手喝采 designed by Ryohei Kazumi
あなたにとってピアノが大事なことは分かっている。でもね、それが何であれ、辛くなった時は逃げてもいいのよ。
いつ辞めたって構わない。そして、やり直すことだって出来るの。それは誰も強制することでは無いの。
リサはそう言ってくれた母に、辞める決断がどんなに怖いか。
自分にひとつしかないものを辞めるという決断をしたことのない母さんにはわからないと、
そう喚き散らした時の、母の寂しそうな笑みを忘れられないでいる。
母の言葉は確かに優しくて、正しかった。
でも、その言葉で安らぐほど、単純で安い女じゃないというプライドがリサにはあった。
リサ・エウトイは、未来のスター発掘と銘打ったテレビ番組に5歳当時、天才ピアニストの触れ込みで取材を受け、
その圧倒的な演奏力と、愛らしいルックスから話題となった。
出演する演奏会は完売を続け、芸能界入りを果たし、スター街道を駆け上って行った。
有り触れた話であるが、成長と共に、世間から興味を持たれなくなり、
成人を過ぎた頃には誰からも見向きもされなくなっていた。
若かりし頃の成功体験は、リサの人格形成に影を落とした。
一度知ってしまった栄光は、プライドを肥大化させ、若い心に贅肉をつけた。
新たな目標を見つけられず、心の中の理想と、鳴かず飛ばずの現状との乖離を、世間の見る目がないのだと言い訳をつけて、
逃げ出さない振りを続けていた。そんな折に、母から投げ掛けられた言葉。それは、確信を突いていた。
今でも、昨日のことのように覚えている。その時の喧嘩が、母との最後の会話になった。それはもう、十年も前の話だ。
この国の冬は長い。止むことのない雪で、街は時間が止まったように静まり返っている。
全てを白く飲み込んで、みんな、何処かにいってしまったように感じる。
顔を刺す北風で、縮む身体を震わせ、リサは目当ての建物へ急ぐ。藍色の壁面のビルに、目当ての店がある。
やっとの思いでたどり着き、重たい扉を開けると、暖かな空気と喧騒が迎えてくれる。
静から動へ、扉一枚隔てて、分断された空間を行き来する時のコントラストが、生きていることを実感させる。
いつものように席は埋まっている。
開店当初は真紅であったろうカーペットは踏み締められて、濁った黒が目立っている。
壁際にある、いつものテーブルに座り、厚手のコートを脱ぐ。
リサはレストラン『アンコール』で週に一度、演奏をしている。
馴染みのウェイターと挨拶をして珈琲を貰う。これを一杯飲んだら仕事の時間。
大きな店では無いが、ここでピアノを弾くのが自分の精一杯。
手を開いては握り、繰り返して、強張りが無いことを確認すると、ピアノの前へ向かう。
自分が自分でいられる限られた時間が始まるのだった。
何時もの客層は、何時もと同じ疎な拍手で応えてくれた。
リサの演奏も何時も通り。
何時ものテーブルに戻ったところ、自分の席に見知らぬ女性が座っていた。
長い黒髪は緩くカーブし、大きくつり上がった眼が印象的だった。
女性はリサを見つけると、微笑んでから簡単な挨拶をし、正子と名乗った。
「いい演奏ね、迷いがあるけど冬に聞くにはちょうどいい」
見透かしたような視線を感じたが、不思議と不快感は無かった。
「あなたがリサね。リサ・エウトイ」頷くリサ。
「やっと会えた。さあ、座って。クッキーがあるの、食べながら話しましょう。積もる話があるから」
正子は、勝手に話を進めると、鞄の中から大ぶりのクッキーと花柄のティーカップを2つ取り出し、テーブルに広げ出す。
まるで、ここが自分の家であるかのような振る舞いだったが、ウェイターは気にしていないようだった。
リサのお気に入りの席は、正子の用意したティーセットでいっぱいになり、いつもとは別空間のようだった。
立ったまま呆けていたリサは正子に促され、席に着く。その様子を見て、正子は満足したのか、また、優しく微笑んだ。
向かい合って正子を観察すると、薄い化粧だが、深く黒い瞳が際立って見える。
黒髪も漆黒そのもので、艶やかに光り、肩甲骨の辺りまで伸びていた。
パンジーだろうか、花の形が連なったネックレスに、刺繍の入った黒のゆったりとしたコート。
若くは見えるが50代後半くらいだろう。記憶を遡ってみるが面識は無いはずだ。
「あなたは忘れてしまったかもしれないけど、私はあなたを知っているわ。
本当は、あなたの演奏を聴いて帰るつもりだったのだけど、懐かしくなってしまって。つい、声をかけたのよ」
リサの視線から察したのか、正子が会話を切り出した。
「あなたは、もう一度、ピアノに本気になるべきね。あなたに才能は無いけど、あなたの血はまだ諦めてないように思うわ」
触れられたく無い話題だった。それに、全てを知っているかのような態度が癪に触る。
「あなたは私を知っていると言う。何時です、何処で会ったのでしょう」
「そのことについては、いずれ時が来たら話しましょう。過去よりも、今はあなたのこれからについての方が大事。
その腕、錆びつかせたままで良いのかしら」
リサの眉がピクリとつり上がる。
「私はここでピアノを弾ければ幸せですし、錆び付かせているつもりはないです」
気丈に振る舞うリサに、正子はゆったりと時間をかけてから「嘘」とだけ言った。
正子の瞳は吸い込まれそうなほどに黒い。心を読んでいるに違いないとリサは思った。
「がむしゃらになって、うまくいかなかった時が怖いのかしら」
ピアノを始めた頃、真綿が水を吸うように、なんでも吸収できた。
言われたことはすぐに出来るようになったし、出来るようになることが嬉しくて堪らなかった。
それに、自分の演奏で喜んでくれる人がいる事は、純粋にとても嬉しかった。
ピアノ椅子の高さにベッドを設置してもらい、一日中、飽きるまで弾き続け、疲れたらそのまま横になった。
リサの生活は常にピアノの前にあった。誰よりも上手に出来るという、根拠のない自信で溢れていたし、
実際に、出来ると思ったことは直ぐに出来るようになった。
リサにとってピアノを弾くことは息をするのと変わらない、当たり前のことだった。
だから、躓き、その当たり前が、当たり前では無くなった時、何をすればいいのか、目の前は真っ暗になった。
がむしゃらになる?そんなこと、当たり前にやって来た。
それでも上手くいかなくなった時、評価される事もなく無視されて、
進むべき道筋が何処を向いているかわからなくなった時、人はどうするのだろうか。
友人もなく、ピアノだけしかなかった自分は、寄る辺を失ってしまった事に気付かぬ振りをして、
それでも、必死に足掻き続けた結果が、この店で週に一度の演奏なのだ。
それを否定する権利があるのかと、正子を睨みつけていた。
「あるわ」
正子はリサを見もせずに、あっけなく答えた。
「あなたには技術はある。でも、問題なのは心。迷ったまま、空っぽのままでいると、心はその隙間を埋めようとする。
あなたは自身を信じきれなくなっているから、他人の言葉や行動に目移りして、誰かの言葉で心を埋めようとしてしまう。
現に、私の言葉で動揺しているのが良い証拠。あなたは過度に自分と他人を比べようとする。それではいけない」
しっかりと見透かされていた。
「どうやら、あなたは私を疑っているみたいね。それでも、あなたの歩みが止まってしまっているのは確かだわ。
そうやって、寄る辺を失ってしまった時、それを自覚することが必要よ。そして、此処までの自分を糧としながら、
その自分を否定しなくてはいけない。ただ、否定して反対のことをすればいいわけじゃない。
なんであれ、自分が今までやってきたことに答えはある。それを信じなくては」
正子の言葉は、あの煩わしさを凝縮した、母の正しい言葉に似ていた。
母との思い出は、喧嘩ばかりだった。
あの煩わしい懐かしさが、正子から放たれる一方的な会話にはあった。
「じゃあ、私に何をさせたいの。まさか、正論を言うために、私に会いに来たとでも言うの
リサの問いに、正子は大げさな調子で立ち上がると、両手を広げて言い放つ。
「私はあなたの緩んだ螺子を締めに来たの。あなたの母から頼まれた最後の仕事を終わらせる為に。
あなたは信じていないでしょうけど、私に出来ないことは無いわ」
そう言い切る正子の瞳は、嘘を付いているようには見えなかった。
「なぜなら私は魔女だから」
リサは朽ち果てたアップライトピアノの前で茫然としていた。
200年前に作られたというピアノは、屋根や上前板がひび割れて、大きな亀裂が入っている。
閉じない鍵盤蓋には、弾痕のような無数の穴も空いていた。
鍵盤は大きく波打ち、いくつもの欠落が見てとれた。
そして致命的なことに、ひとつとて、鍵盤から音が鳴ることはなかった。
半ば強引に連れてこられた正子の屋敷で、リサはこの朽ちたピアノで弾けるように成りなさいと言われ、立ち尽くしていた。
使いこなすまでこの部屋から出られないと正子は告げ、実際に金網で遮られた部屋は独房そのものだった。
考えるまでもなく、これは立派な拉致監禁だった。
それでも、正子の言葉に動揺し、ピアノのことを考えずにいられなくなっている自分は、
もう、おかしな人間になってしまったのだ
と思うと、不思議と冷静になった。
朽ちたピアノでの練習は、当然ながら難航を極めた。何せ、音が鳴らないのだ。
何を目的に練習するべきか、そこから考える必要があった。
数日はピアノの前に立ち尽くして終わり、半分も残っていない鍵盤を、ただただ叩きつけるように弾いて、
1日を潰すこともあった。
どうにかピアノを直せないものかと大きく空いた亀裂から中を覗いてみたが、混沌とした内部は見るも無残で、
時間とやる気を無駄にするだけだった。
そうやって、数日が経った深夜、朽ちたピアノを眺めながら、ふとした拍子に、自分に似ていると独り言を呟いていた。
はたと我にかえると、やはり、ピアノは自分と似ているように思えた。
すると、どうにか、このピアノと友人関係になれないものかと考えるようになっていた。
そこで、ピアノを綺麗に拭き上げる事から始める事にした。
内部を直すことは出来ないが、せめて、外側だけでも、大きく入った亀裂に、丁度良いサイズの木材を当ててやり、
無くなった鍵盤には、おもちゃの積み木を並べ、錆びついたぺダルには靴下を履かせてやった。
そして、そもそも無かった椅子の代わりに、ベッドを運び入れて設置すると、ピアノは見違えたように見えた。
音が鳴ることは無いが、このピアノならば、自分の演奏が出来る。自分でも笑ってしまう、可笑しな確信があった。
その思いのままに、積み木で七色になった鍵盤を奏でた。
朽ちたピアノはリサの頭の中で、美しい音色を奏で始めた。
そこからは、長年の鬱屈とした想いを吐き出すかのように、時間に囚われること無く、演奏を続けた。
いつ寝たのかも記憶が曖昧なくらい、弾き続けたリサは、ピアノを弾く自分を俯瞰で見ている感覚すらあった。
俯瞰で見る自分は、小さく痩せ細って見え、独りで弾くのが可哀想なほどだった。
ふつふつと湧いてくる、遣る瀬無い気持ちを振り払おうと、自分の隣に座り、連弾してみることにした。
カノンや花のワルツ、ラフマニノフと思いつく限りの曲を、自分と二人で弾き続けることで、
細い腕と腕が絡まり合い、寸分の狂い無く、理想の音を奏でた。
その時初めて、自分で自分を褒めてあげたい気持ちになった。
自分を許すことが出来るかもしれない、そう思うと涙が止まらなかった。
全てはリサの頭の中で起きている妄想の産物にすぎない。
しかし、確かにリサは自分と連弾をし、そこには自らを許すに足る説得力があった。
「いい顔になったね」
朦朧とする意識の中で、誰かにそう言われ、肩を叩かれた気がした。
それが自分だったのか、それとも正子だったのか。もうわからなかった。
暗闇が広がるステージの上では、伸ばした指先が何処へ落ち着くのかわからない。
客席から聞こえる囁きは、重なりあって騒めきになっている。高い音の咳払いが遠くで聴こえる。
客席とステージの間を分断する形で、金網や穴が無数に空いた壁面が設置されている。
金網には、蝋燭の灯りで薄ぼんやりと照らされたパンジーの花束が括り付けられている。
客席からは、照明の落ちたステージの様子は窺い知れない。
リサの指先がようやく鍵盤に辿り着き、優しく黒鍵をなぞる。
始まりの鍵盤を見つけると暗闇の中で瞼を閉じた。
雑音が途切れる僅かな沈黙に合わせて、眼を開けると同時に鍵盤を叩く。
視界は変わらない暗闇の中。聴衆が静まり返る。
リサは本名では無く、hands と名乗るようになった。
自分との連弾という経験が、大きな転機となり、
自分の中に内包されていた、苛立ちや苦しさを受け入れ、自分を許すことに繋がっていた。
朽ちたピアノでの演奏を達成した後も、正子からは自動演奏する電子ピアノに、
登録されていない曲を閃かせるまで連弾させられたり、ドラマーのコンクールに音の出ない
朽ちたピアノでエントリーし、打刻音だけで客を沸かせろといった無理難題を幾つも出された。
そして、その全てを退けるうちに、親子程、年齢の離れた正子との間に、友情に似た感情が芽生えていた。
それは、もはや叶わない母との和解のようで、心に出来たしこりが、小さくなりつつあるのを感じていた。
正子には何か、思惑があって近づいたのだろうとリサは考えている。
彼女との出会いはリサにとって天災みたいなものだった。
それでも、自分がこんなにも変わっていくなんて想像すらしなかった。
変わらぬはずの生活が、突然、転倒を起こす。
それまでの見方が、正子との出会いを境に一変した。
終わりなき日常は緩やかに、しかし確実に変化している。
リサ自身、全てはそうやって変わっていくと、そう、気づくのに時間がかかってしまった。
この演奏が終わったら正子には洗いざらい喋って貰おうと思った。
今日の演奏は一度きり。全霊の演奏中にも関わらず、心は落ち着いている。
眼を開けても、閉じても何も変わらず暗闇だけが続く。
それでも自分の隣には信じられる自分がいた。
鳴り止まない拍手の中、ステージを後にする。
私の魔女は、微笑んでクッキーを手渡して来た。
texi by Takaaki Akaishi
Ryohei Kazumi 数見 亮平
1984年東京生まれ。アーティスト。
絵画や版画など様々なメディアによる作品や、zine、オリジナルグッズなども制作。
架空のミュージアムショップことENTERTAINMENTを主催。
Takaaki Akaishi 赤石 隆明
1985年静岡生まれ。アーティスト。
写真を媒材に立体や展示空間へと展開させ、作品を次々とアップデートしていくなど
写真というメディアに対して挑戦的に取り組む。
TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD (2012) グランプリや「あいちトリエナーレ2016」などに参加。
STANDARD AUTHENTIC SHIRT
COTTON 100%

ご注意
*染めを含む加工を施しているため、実寸サイズには2〜3cmの誤差が生じる可能性があります。ご了承下さい。